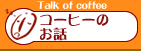|
||||||
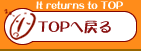 |
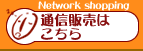 |
|
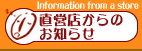 |
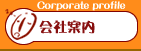 |
| ナガハマコーヒー>>コーヒーのお話リスト>>コーヒーのお話 |
| コーヒー全般 1 | |
| コーヒーの歴史・2つの起源説 |
| これだけ世界中に広まっているコーヒーですが、自生していたコーヒーがいったいどのような経緯で人間に発見され、そして現在のように飲料として世界各国に広がっていったのでしょうか?数多くのコーヒー起源伝説がありますが、その中でも特に有名な2つのコーヒー伝説をご紹介いたします。 |
| 「ヤギ飼いガルディの話」(エチオピア起源説) 6世紀頃のエチオピア高原での出来事です。 ヤギ飼いガルディは、ある日放し飼いにしていたヤギ達が昼夜の区別なしにひどく興奮し続けているのを発見しました。色々と調べてみると、どうも丘の中腹に自生している灌木の赤い実を食べたらしいという事をみつけました。近くの修道僧にこれを相談すると、それでは試しに食べてみようということになり、食べてみると体に活力がみなぎり、気分はグングン爽快になってきたのです。 修道僧はこれはいいと早速僧院に持ち帰り、他の修道僧にも勧めました。それからは、徹夜の宗教行事のときに睡魔に苦しむ僧はいなくなり、「眠りを知らぬ修道僧」とまで言われるようになったそうです。 「回教僧シェークオマールの話」(アラビア起源説) 13世紀頃のイエメン山中での出来事です。 回教僧のシェーク・オマールは、無実の罪でイエメンのモカからオーサバというところへ追放されてしまいました。彼は食べるものもなく空腹に耐えながら山中を歩いていると、色鮮やかな鳥が飛んできて木の枝にとまりました。その鳥はとまった木の赤い実をついんばんでは陽気にさえずっていました。それを見つけたオマールは赤い実を口に含み渇きをいやしました。そしてポケット一杯にそれを詰め込み、試しに赤い実を鍋で煮てスープを作って飲んでみると、今までの疲れがウソのように消え去って元気が回復しました。その後医者でもあった彼はこの実を使ってたくさんの病人を救いました。そして罪を許されて再びモカに帰り、その後は聖者としてあがめられたということです。 |
| 効能 |
| これだけ世界中に広まっているコーヒーですが、飲んでいる人にはどのような影響を与えるのかご存知でしょうか? コーヒーの成分の中ではカフェインが有名です。カフェインはアルカロイドという物質の一種で、脳に働きかけてアドレナリンの分泌を促す作用があります。紅茶や緑茶にも含まれていますが、アドレナリンの分泌促進はコーヒーが一番強いようです。 アドレナリンが分泌されると、肝臓に蓄えられていた栄養(グリコーゲン・たんぱく質・脂肪など)が血液中に流出します。このグリコーゲンはアドレナリンによってブドウ糖に分解され血液中へと流れるので、その結果脳や筋肉の隅々までブドウ糖が行き渡り、血糖値が上がってエネルギー代謝が起こります。 |
| 効能・1 気分転換・眠気覚まし カフェインの作用で脳にブドウ糖が行き渡り頭の働きがよくなるので、気分転換や眠気覚ましには最適です。これから行動を起こそうとしている時、行動や考えを切り換える時などに飲む1杯のコーヒーは素晴らしい効果を発揮します。また、低血圧の人が朝にコーヒ−を飲むと血糖値が上がり一時的に血行がよくなるので、スッキリ起きられます。目覚めの一杯をミルクたっぷりのカフェオレにすると、胃壁を守りつつ爽快な気分になれるでしょう。 効能・2 リラックス いい香りは精神の緊張をほぐし、気持ちを安定させてくれます。また、最近よく耳にする「α波」は特別なものではなく、気分が良い時や楽しい時に出るものなので、コーヒーの香りをかぐと「α波」が出て自然と気持ちがゆったりします。 さらに、コーヒーを飲むと血糖値が上がり脳が集中力を高めるので、冷静な気持ちで物事に取り組む事が出来ます。 効能・3 ダイエット カフェインの作用により分泌されたアドレナリンが脂肪細胞に入ると、脂肪の固まり(脂肪球)が細かく分解されて血液中に流れます。ここで運動すると脂肪の細かい粒が筋肉細胞に入り効率良くエネルギーを燃焼します。しかしこの効果は2時間程度しか持続しないので、せっかく飲んでも運動しなければ意味がありません。 効能・4 消化促進と口臭除去 アドレナリンは交感神経を刺激し胃酸の分泌を促すので、食後のコーヒーは消化を助けてくれます。 コーヒーに含まれるタンニンににおいの成分がくっつく事により、食後の口臭が気にならないようになります。 効能・5 疲労回復 ブドウ糖が体に行き渡って元気が出るので、疲れがとれたと感じるはずです。でもこれは一過性で効果は2時間程度です。ただし精神的疲労回復という点では効果絶大です。 |